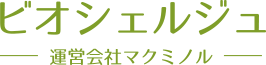南伊豆アボカドプロジェクト 2017年秋の現地の様子をご報告いたします!
当初11/12(日)の訪問を予定しておりましたが、農園の都合と天候の影響により二度の日程変更をすることになってしまいました。お忙しいなか、当初の日程で調整されていた参加者の皆様には、大変申し訳ありませんでした。今後このようなことがないように努めてまいります。
11/26(日)に現地・マザーアースクラブを訪問し、苗木の成長を確認するとともに、冬越しの準備作業をやってきました。その模様を写真とともにご覧ください。
苗木の生育



【比較用】2016年10月に植えた当時の苗
苗は元気に育っております!
写真で見ると、なんだか細いけど大丈夫?とお感じになるかもしれませんが、一年前に植えた当時の苗と比べてご覧ください。
最初は1本の幹しかなかった苗が、2本3本と枝分かれし、背が伸び、葉の数も増やしているのがわかりますね!
ただ正直なところ私たち自身も、もう少し大きくなるかな、と思っていた部分はありました。苗木をお世話していただいているマザーアースクラブ・石川さんは、この原因と対策を次のように考えていらっしゃいます。
- 昨年秋(第1回植樹祭)に植えた苗木は、冬越しには問題なかったものの、その後の成長が遅かった。今年春に植えた苗の方が、根がしっかりと張り、成長が良い
→ 秋植えは止める。苗はハウスで冬越しさせ、春に定植する - 今年7月の成長期に雨不足に見舞われた。手作業で灌水(水やり)したが、それでも足らなかった可能性がある
→ 来年は川からポンプで水を汲み灌水できる設備を整える
苗木も着実に成長していますし、石川さんも南伊豆の地でアボカドを育てるノウハウを積んでいらっしゃいます。来年に期待ですので、引き続きご支援よろしくお願いします。
冬越しの準備作業
さてここからは、苗木が今年も無事に冬を越えられるよう、防寒対策を施していきます。
と、その前に苗木を見ると、昨年の第1回植樹祭で付けた名札が、1年の雨風に晒され、こんなになっていますね…


そこで、まずは名札を更新しましょう、ということで新しい名札を作りました。
これを持って、いざ、アボカド果樹園へ。

冬の対策で重要なのは、風除けです。
アボカドの苗木は気温 -2℃ 〜 -5℃ あたりまで耐えられる品種を選んでいますので、南伊豆なら冬でも温度は問題ありません。ただ冬は強風の吹く日が多いです。葉が強風に長時間煽られ続けたり、吹かれた枝や葉がぶつかり合って傷つくと、冬にはそこから枯れてしまう場合があるので、防風の囲いをします。



最初に、苗木と添え木を結んでいた紐を取り替えます。これも、固い素材だと幹を傷つけてしまいます。新しくいい素材が見つかったので、今回取り替えました。
これが実は、網戸の張替えに使うゴムなんです。適度な強さと柔らかさがあるのと、ホームセンター等で、いつでも安価に手に入るということで採用になりました。



次に支柱を追加し、白い不織布でグルっと囲みます。この薄い布は、光を通しながらも風を弱める効果があります。
最後に、支柱に新しい名札を取り付けて、完成です!
この名札も苗木に直接くくり付けると、風に揺られて幹に擦れて、木を傷めてしまうことになるため、支柱に付けます。
もうちょっと木らしく立派に育った暁には、幹に付けられるようになります。



この日は定植済みの苗木の冬囲いを行い、約半数の方の名札を取り付けてきました。
残りの苗木は、このままハウスで冬を越させて、来年春に定植します。
一部の方の名札は、来年春に植える苗に取り付ける予定ですので、お楽しみにしていてください。(参加者の皆様には、個別にメールでご報告いたします)


ハウスの様子
アボカドの苗木が冬越しをするハウスの様子を見ておきましょう。
南国ムードたっぷり!パッションフルーツの実が成り、ゼラニウムの花も咲いています。





ドラゴンフルーツも実が成っていました。
食べごろに熟したやつを一つ、いただいちゃいました。甘〜い!
残りの苗木たちは、こんなハウスの中でぬくぬくと冬を過ごしてもらい、来年春にデビュー(植え付け)する予定ですので、楽しみにしていてください。
なお、低温に備えて薪ストーブもスタンバイしていますので、ご安心ください!



おまけに、ハウス内で保管されていたもの。
最初の写真がマコモダケの皮にレモングラス、これでハーブティーが作れるんだとか。
次の写真は綿。決して汚れてるんじゃなくて、こんな色の品種なんだそうです。
農家さんも次々と挑戦されますので、農園を訪れる度に新しい発見があります。
みなさんも、ぜひ一度、足をお運びください!
おまけ:伊豆の車窓から
これまで車で片道4〜5時間かけて現地訪問しておりましたが、今回初めて電車で行きました。



片道2時間ちょい…なんと車の半分…しかも座ってるだけ…なんて楽なんでしょう!
車窓からは相模灘…伊豆大島も良く見えました…快適すぎる!
 交通費は少し高くなりますが、これはもう次回からも電車だな、と心に誓いつつ帰りの踊り子号に乗り込んだのでありました。
交通費は少し高くなりますが、これはもう次回からも電車だな、と心に誓いつつ帰りの踊り子号に乗り込んだのでありました。
取材日:2017/11/26
今回のご報告はここまでです。いかがでしたでしょうか?
次回の現地訪問は2018年4月中旬を予定しています。また近くになりましたらご案内いたしますので、ぜひご一緒しましょう!
プロジェクト参加者も引き続き募集しています。ご参加お待ちしています!