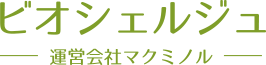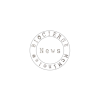新シリーズです。有機農産物の流通を担う業者どうしの対談企画がスタートします。
新シリーズです。有機農産物の流通を担う業者どうしの対談企画がスタートします。
オーガニック野菜って高い?いまいち広まってない?といった業界の課題から、今後の取り組みまで、お互いに腹を割って語り合います。
たっぷり紙面を割いて同業者を紹介するという、ある意味斬新な企画です。
第1弾は、スィンセリティの伊佐治幸樹さんです。
お父様が始められた有機野菜の卸売業を引き継ぎ、岐阜県美濃加茂市を拠点に、全国から有機野菜を仕入れ、また全国の小売店、飲食店に販売されています。

【伊佐治】伊佐治幸樹さん
両親の愛情から始まったオーガニックの八百屋を継ぐ
【伊佐治】親父が平成3年に始めて、27年目ですね。
【伊佐治】もともと曽祖母の代からの八百屋を父が継いでいて、母はエステを経営していました。僕が生まれて、3歳~5歳の間、アトピーが酷かったんです。それで父と母が、何かできないかと勉強していくうちに、無農薬野菜が良いんじゃないかと行き当たって、僕専用に買ってきて食べさせるようになったんです。
【伊佐治】他にも食品添加物に気をつけるとか、色々やったんですが、僕の場合は、それを1年ほど続けているうちに、どんどんアトピーが緩和されていって、表面上はほぼ治ったんですね。でも体質は残っているだろう、という中で、今後の食べ物をどうしていくか考えたそうです。
自分の子供がこれだけ治ったんだし、やっぱり誰がどう作ったかわからないものを市場で仕入れて売るよりは、作る人も栽培方法もわかった野菜を売っていきたいと、父も心を決めたそうです。
 【伊佐治】そこで30年続いた八百屋を一回止めて、借金して社屋も一新して、自然食品店という形でスィンセリティをスタートさせたんですね。でも、なかなか売り上げが伸びず、この先どうしようか?という話になりました。
【伊佐治】そこで30年続いた八百屋を一回止めて、借金して社屋も一新して、自然食品店という形でスィンセリティをスタートさせたんですね。でも、なかなか売り上げが伸びず、この先どうしようか?という話になりました。
ただ父は産地との繋がりを作るのが非常に上手な人でして、特に北海道と九州の有機農家さん、それも大量に作れる生産者との繋がりが多かったんです。そこで、全国の自然食品店に電話をかけ回って、あちこちから少量で仕入れると運賃が大変ですよね、うちが一括で大量仕入れして分けることができますよ、とまぁ、卸売業ですよね、それを平成4年から始めることになりました。そこから今に至ります。
【伊佐治】平成21年ですね。今年で9年目です。
【伊佐治】一つのきっかけは、大学で救急救命を学んだことです。救命の仕事を目指していましたが、毎日人が亡くなる環境、もう亡くなった方を大事に扱うのが難しくなるくらい毎日次々と運ばれてくる、という環境で4年過ごしてみて、これを60歳まで続けるのは、正直辛いなという思いがあって、救命の仕事は諦めたんです。
【伊佐治】それで次の進路を考える時に、やっぱり自分のアトピーがきっかけで、父が大きな覚悟を決めて会社を作ってくれたので、それを継ぐのが良いいんじゃないかと。
大学4年間で人の命に関わる勉強をさせてもらいましたが、その中で「最期、亡くなる時が人の完成形だ」という言葉があったんです。うちの父もいつか亡くなる時が来ますが、最期に「この会社を作って良かったな」って言葉を吐かせてあげたいなという思いがあったので、後を継ごうと決めました。
【伊佐治】ただ大学を出ただけの社会も野菜も知らない人間が入ると、足手まといになってしまうと思ったので、最初は大学で学んだ事も活かせる医療メーカーに就職して、営業をやったんです。外資の会社で、3年で満足のいく結果を残すと決めて、その目標を達成したので、スパっと辞めて、この会社に入って9年目、というところです。
【伊佐治】一番最初にやったのは、経理の仕事です。農業とか八百屋の業界は、良くも悪くもどんぶり勘定の部分があるので、そこを改善した方がいいだろう、という思いは入社前から持っていて、入って最初に経理を見させてもらいました。その次に、父と一緒に産地回りをして野菜を覚えて、それから徐々に営業をスタートするようになりました。
 ― 外資系だと、とにかく数字で見られますよね。一方でオーガニック野菜の世界は、数字以外の、何か違う原理で動いているようなところがありますよね。最初に入った時に、どう思いました?
― 外資系だと、とにかく数字で見られますよね。一方でオーガニック野菜の世界は、数字以外の、何か違う原理で動いているようなところがありますよね。最初に入った時に、どう思いました?【伊佐治】かなり「独特」ですよね。言葉の選び方がすごい難しいですけど(笑)
【伊佐治】商売って、お客様が中心に回ると思っていたのですが、そこが逆、売り手・農家側が優位で、買い手は「買わせていただいている」という立場の業界なので、最初は大いに戸惑いました。何なら今でも(笑)
【伊佐治】農家さんも職人気質で、商売には慣れていないというか、売買契約を結ぶっていう事自体にあまりピンときていない人も多いんです。一度決めた価格を後から覆されたりします。それでも買い手側は欲しいので、言うことを聞く。需要と供給のバランスがずれているところがあるので、しばらくはこの状態は変わらないだろうなと思っています。
【伊佐治】その違和感が無くなることはないんですけど、自分にとっては強くて怖くて威厳を持っていた父が、こと商売においては、農家さんに頭を下げているという姿、20年一人で頑張って積み重ねてきた人が、その姿勢っていうのを見た時に、あぁ、こういう世界なんだなと自分の中でも落とし込むことができました。その分、気は楽になったと思います。
「父と子」そして「社長と社員」
【伊佐治】ビックリしましたね。僕が子供の頃、父がカボチャの取引で当たって、すごく良かった時期があったんですが、そのイメージが強かったんです。その後、大学は東京、就職は名古屋と、あまり実家に帰らず知らなかったんですが、実は会社にとっては、その7~8年が特に苦しい時期でした。戻ってみると、父も年をとって痩せてましたし、経営状態を見た時には本当にビックリして、一度は会社をたたむべきなのかと考えたこともありました。
でも大学を出る時に決めた心、父の会社を必ず残したいという思いがあったので、家族とも色々と話をして、期限を決めて、頑張っていこうということになりました。
 【伊佐治】2年ですね。最初の2年間は赤字。特に、一度会社の勢いがなくなると「お前のとこの会社、大丈夫か?」という声が最初に出てくるようになるので、そこの信用を取り戻すのが大変でしたね。例えば先入金や担保を求められたり、そのお金のやり繰りで銀行へお願いに行ったり。25~6歳の人間が人の信用を勝ち得るって、すごい難しいものだし、まだ野菜の業界のことも分かっていない、ハードルがいくつもあって、すごいストレスで、しんどかったです。
【伊佐治】2年ですね。最初の2年間は赤字。特に、一度会社の勢いがなくなると「お前のとこの会社、大丈夫か?」という声が最初に出てくるようになるので、そこの信用を取り戻すのが大変でしたね。例えば先入金や担保を求められたり、そのお金のやり繰りで銀行へお願いに行ったり。25~6歳の人間が人の信用を勝ち得るって、すごい難しいものだし、まだ野菜の業界のことも分かっていない、ハードルがいくつもあって、すごいストレスで、しんどかったです。
【伊佐治】まぁ2年でようやく、売上が少しずつ上ってきて、赤字だったんですけど少しずつ減ってきて、この先ちょっと面白い流れが作れるんじゃないかな感じられるようになったのが3年目ですね。
その辺の葛藤とか気持ちの整理ってどうしてますか?
【伊佐治】確かに父の下に入るっていうことには、違和感はありましたよね。父のことを、なかなか「社長」とは呼べない。当時、まだまだ子供だったなと思うのですが、仕事の中でも「親父」と言ってしまいますし、ぶつかることもありました。プラスに向かう議論もありましたが、ただの親子喧嘩っていう時もありましたし、他の従業員には申し訳なかったです。今からすると無駄なエネルギーだったな、と思います。
【伊佐治】それなりに続きましたね。ただ3年前、自分が6年目の時に父が病気をしてしまって、入院することもあったので、そこからは私が中心に会社を運営するようになりました。
人と人の繋がりを作る仕事
【伊佐治】父の時代は、基本的にはタウンページを開いて、電話をかけて「農業やってらっしゃいますか?」から話を始めて…
【伊佐治】そうです。で、1軒見つかると、やっぱり地域って横の繋がりがあるので「こういう野菜を探しているんです」って言うと「じゃ〇〇さんがそういうの作ってるから」って紹介してもらって、そしたらすぐに現地に飛んで話をさせてもらう。取引が始まると「そんなに動くんだったら、こっちも紹介するよ」って紹介が広がって、その地域で増えていくっていう流れでしたね。
【伊佐治】父の時も八百屋としては後発なので、やっぱり端境期のお野菜をメインに販売しようと考えて、北海道、九州に頻繁に足を運びました。父は現地のリーダーというか、それこそボスみたいな方々とは、もうすごく仲良くなっていて、おかげで僕もそういう方々から可愛がってもらっているので、やはり農家の開拓っていう部分は、まだまだ父には敵いません。現地のキーマンが残っていらして、そこから自分たちが仕入れ先の農家さんを増やすこともできるので、本当に助かっています。
【伊佐治】そうですね。僕ら八百屋の生産性、生み出す価値ってなんなの?って言われた時に、すごく難しくて、何もないと言えば何もないですよね。人を繋いで紹介をして、言葉を変えるとブローカーみたいなもので、そこで信用を得るって難しいことだと思います。そういう意味で、売るものを分けてもらっているっていうのは、非常にありがたいことだと思っています。
 ― そういえば、スィンセリティさんとマクミノルと、最初の繋がりって何でしたっけ?
― そういえば、スィンセリティさんとマクミノルと、最初の繋がりって何でしたっけ?【伊佐治】そうです。で、すぐに続いてキャベツの注文もいただいたんですよね。キャベツが本当に品不足の年で、九州各地を探し回りましたよ。
【伊佐治】そうですね。それでクレーム言われる度に、産地変えて、産地変えて、ってやってると、松野さん(編者注:取材当時のビオシェルジュ運営会社・株式会社マクミノル代表)から「産地スゴい抱えてるね。キャベツでそんなにあるんだったら、他の野菜もあるの?」っていう話になって、そこから取引が少しずつ増えていきましたね。
【全員】(笑)
「横の繋がり」が業界を変えていく
【伊佐治】はい。
【伊佐治】そうですそうです。
 ― それで野菜がある、ない、足りないとか言うんだったら、我々みたいな業者どうしが繋がって、物を融通しあえば早いんじゃないの?そういうことを誰も考えないのかな?っていうのが不思議だったんです。
― それで野菜がある、ない、足りないとか言うんだったら、我々みたいな業者どうしが繋がって、物を融通しあえば早いんじゃないの?そういうことを誰も考えないのかな?っていうのが不思議だったんです。【伊佐治】不思議ですね。
お互い分かり合ってたら、10円引いてとか、イヤだとか、しょうもない駆け引きをしなくていいし、話が早いんですよ。
【伊佐治】そうですね。
【全員】(笑)
【伊佐治】僕もこの業界に入って、同じ部分に一番最初に引っかかったんです。
ただ仕事を続けているうちに何となくわかったのですが、僕ら中間業者って、売る野菜があって初めて商売できるので、何としてでも野菜を確保したい、その延長上で農家を囲うんじゃないかと。それに有機の需要は伸びていて、生産が追いついていない部分もあります。実際に生産者から「もう全部、売り先が決まっているから、君には売れないよ」と言われることもあります。そんな中で自分たちが売る分を確保しようとする、もう先駆者である大手業者がそういうやり方で、農家さんに「作物の〇割は、うちが契約するから、他には売らないでね」と買い受けたり、前金を払っていたりします。農家さんも、その部分は囲ってしまう。そういう業界なんだと思っています。
 【伊佐治】僕は農家さんには、そういうやり方は変えていった方がいいですよ、と言っています。弊社の場合は、大手業者よりは高く買えますよ、スーパーの小売だけじゃなく業務用や加工用もあるので、B品まで買い取れますよ、と。量にしても、松野さんと同じで、業者どうしの連携で増やしていけますよ、と。そうすれば農家さんの収入も上がってきますよね、という話をしています。そこを理解して協力してくださる農家さんも増えてきましたね。
【伊佐治】僕は農家さんには、そういうやり方は変えていった方がいいですよ、と言っています。弊社の場合は、大手業者よりは高く買えますよ、スーパーの小売だけじゃなく業務用や加工用もあるので、B品まで買い取れますよ、と。量にしても、松野さんと同じで、業者どうしの連携で増やしていけますよ、と。そうすれば農家さんの収入も上がってきますよね、という話をしています。そこを理解して協力してくださる農家さんも増えてきましたね。
【伊佐治】価格の話のついでに言うと、既存の業者が利益を取り過ぎ、っていうのも感じるんですよね。さっき言った「大量に買う大手業者さん」彼らが、実際に幾らで小売りしているよ、っていう話を農家さんにすると「え?マジで?」ってなるんです。オーガニック野菜と慣行野菜(編者注:農薬や化学肥料を使う一般の農法で栽培した野菜)の小売価格を比較すると、平均で1.5倍(オーガニックの方が高い)という話があって、運賃の問題(編者注:農協便、市場便と言われるトラックが使える慣行野菜は運送費が圧倒的に安い)もあるんですけど、既存の業者の利幅も大きいんじゃないかと。大手業者さんは、社員が多いので、その分だけ利益を取らなきゃいけない仕組みは分かるんです。
【伊佐治】僕らの規模だと、そこまでの管理はいらない。その分だけ、人件費を抑えることができるので、そういう中小企業どうしが手を取りあってやることで、農家さんにも利益が還元できるし、一般の消費者にも広がっていくことになると思います。その流れを作っていきたいと考えています。


取材日: 2018/02/20
後編「これからの有機の流通の形」に続きます。

スィンセリティさんとマクミノルが全国から選りすぐったお野菜は ビオシェルジュ で注文を承っております。
ぜひログインしてお確かめください。